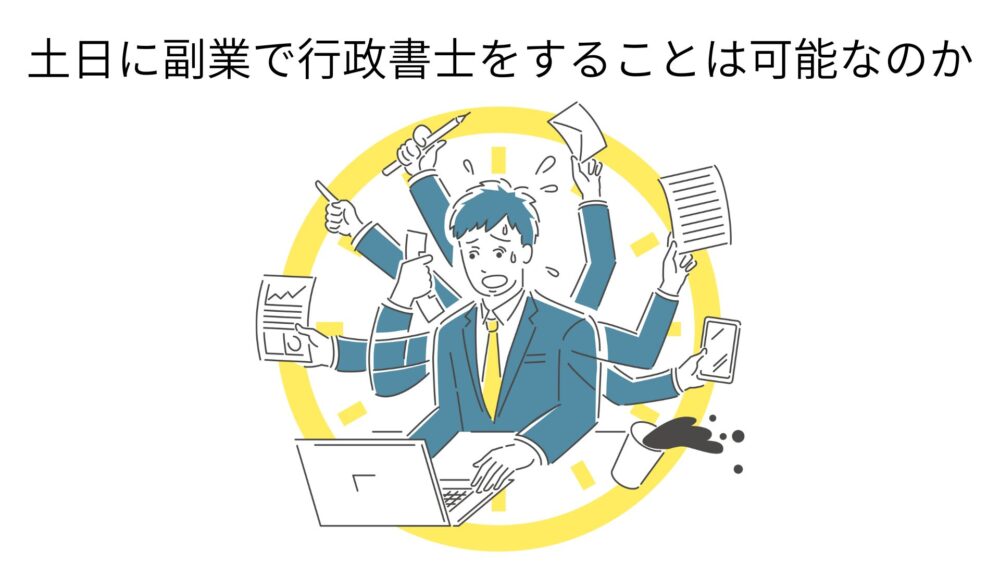今回は会社員の副業として行政書士を選ぶことは可能かについて考えていきます。
結論から言うと、いくつかの条件をクリアできれば可能だと思います。
ただし多くの人にとっては難しい壁になると思います。
今回の記事では、以下の点から副業としての行政書士について考えていきます。
・ 副業としての行政書士が難しい理由
・ 副業としての行政書士が向いている人
・ 副業としての行政書士に向いている業務
それでは早速考えていきましょう。
副業としての行政書士が難しい理由
公官庁は土日祝に開いていない
行政書士の主な業務は「許認可」に関する業務です。
そして、その許認可には公官庁での手続きが必要になってきます。
肝心の公官庁は基本的に平日にしか開いていません。
会社員で平日休みではない場合、公官庁での手続きがほぼできません。
行政書士のメインストリームの業務を行えないのはデメリットとして大きいです。
他士業との連携も難しくなる
行政書士は他士業と連携して業務を行う場合も多くあります。
他士業の先生も多くは公官庁のスケジュールに合わせて動いています。
このように他士業との連携が必要な業務を行うことも難しくなるのです。
営業活動が中途半端になる
行政書士事務所の命綱でもある営業活動ができないのは大きなデメリットです。
平日勤務の会社員の場合、リアルな営業活動はほぼできないといっても過言ではありません。
インターネットを使った場合でも、少ない時間で業務と両立することはかなり難しいでしょう。
このように営業活動が中途半端になるか、力を入れても業務が中途半端になりやすいのです。
また、お客様からの電話に出られない可能性が高いことも大問題です。
お客様に対してしっかりとしたサービスの提供ができないデメリットは大きいでしょう。
ランニングコストがかかる
行政書士になるためには必ず事務所を設けなくてはなりません。
私の場合、行政書士事務所の運営にかかる毎月の費用は、以下のとおりです。
・ オフィス賃料 → 30,000円
・ 通信費 → 10,000円
・ 交通費 → 20,000円
・ 行政書士会費 → 10,000円
大きいデメリットを抱えた上で、これだけ稼ぐのでもかなり大変です。
その上で利益も出すとなるともっと大変になります。
それでは、自宅を事務所にするのはどうでしょうか?
結論としては、身の危険と引き換えになるのでおすすめしません。
行政書士の事務所はインターネットで公開されています。
会社員が自分の自宅を世の中に公開したとしたら何がおこるでしょうか?
会社に通勤している時間を狙った空き巣に入られる可能性もあるでしょう。
ストーカーの餌食になってしまう可能性もあるでしょう。
このように自宅を世の中に公開することには大きいデメリットがあるためおすすめしません。
就業規則で副業が禁止されている場合がある
これは行政書士を副業とする場合には限りませんが重要なので加えました。
就業規則は会社のルールで違反すると懲戒処分の対象になる可能性もあります。
自分の会社が副業を禁止していないかは必ず確認するようにしましょう。
副業としての行政書士が向いている人
副業としての行政書士が向いている人は、以下にあてはまる人です。
・ 平日に休むことができる人
・ 独身等で本業外で時間が多く取れる人
・ 自宅以外に無料で使えるオフィスを構えられる人
これらは副業としての行政書士が難しい理由を踏まえてだした結論です。
これらすべてに当てはまる場合、行政書士を副業とすることを検討してもよいでしょう。
副業としての行政書士に向いている業務
副業としての行政書士に向いている業務は、以下の業務です。
・ 契約書業務
許認可業務を避けて、他士業との連携が必要な業務も避けると残るは「契約書業務」です。
契約書業務なら公官庁の手続きもないですし、行政書士単独で遂行できます。
ただし、弁護士と違い行政書士の契約書業務には限界があることには注意が必要です。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
ここまでお伝えしてきたことをまとめていきたいと思います。
副業としての行政書士が難しい理由は、以下のとおりでした。
・ 公官庁は土日祝に開いていない
・ 他士業との連携も難しくなる
・ 営業活動が中途半端になる
・ ランニングコストがかかる
副業としての行政書士が向いている人は、以下のとおりでした。
・ 平日に休むことができる人
・ 独身等で本業外で時間が多く取れる人
・ 自宅以外に無料で使えるオフィスを構えられる人
副業としての行政書士に向いている業務は、以下のとおりでした。
・ 契約書業務
今回は、以上となります。
この記事が行政書士の開業を考えている方の参考になれば幸いです。